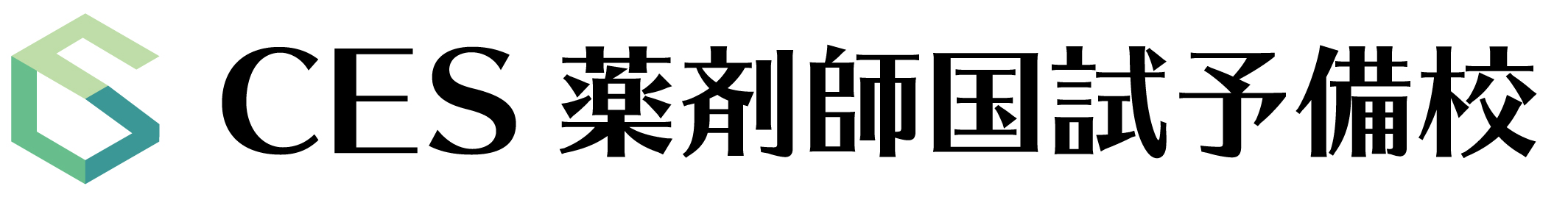病院薬剤師の仕事内容を徹底解説|チーム医療のリアルと1日の流れ

「病院薬剤師って、調剤室でひたすら薬を出しているイメージ」と思っていませんか?
実際の現場では、病棟に出て医師や看護師と一緒に患者さんを支えたり、栄養や感染対策の専門チームに入ってディスカッションしたりと、「チーム医療の一員」として動く場面がとても多くなっています。
ここでは、病院薬剤師の仕事内容・1日の流れ・年収のイメージ・向いている人の特徴まで、薬学生向けに分かりやすくまとめていきます。
大学病院・総合病院・中小病院で何が違う?
一口に「病院」といっても、規模や機能によって薬剤師の仕事の色合いが変わります。
大学病院は高度医療や難治症例が集まり、がん、移植、希少疾患など専門性の高い領域を扱うことが多いです。新薬や治験、ガイドラインの動向など、常に新しい知識をアップデートし続ける必要があり、「とことん勉強したい人」「専門分野を極めたい人」には向いている環境です。
総合病院は、内科・外科・小児科・整形外科など多くの診療科を持ち、地域の中核として幅広い患者さんを受け入れています。救急もある病院では、急性期の治療に関わることも多く、「幅広い症例を経験したい」「臨機応変に動くのが好き」というタイプが活躍しやすいです。
中小病院や療養型病院では、高齢の方の慢性疾患やリハビリ期の患者さんが多く、長く同じ患者さんと関わる機会が増えます。処方提案よりも、生活背景や服薬状況を含めたサポートが重要になり、「患者さんとじっくり関係を築きたい」人に向いていると言えます。
どの病院が良い・悪いではなく、「自分はどんな患者さんと、どんな距離感で関わりたいか」で選び方が変わってきます。
病棟業務・チーム医療の中での役割
病院薬剤師のイメージを大きく変えるのが、病棟業務とチーム医療です。
病棟常駐の薬剤師(病棟薬剤師)は、毎日病棟に上がり、入院患者さんの処方内容・検査値・症状をチェックします。腎機能や肝機能を見ながら投与量を調整したり、飲み合わせのリスクを医師に提案したり、点滴・注射薬の管理をしたりと、「薬の専門家」として診療チームの中に入るイメージです。
また、NST(栄養サポートチーム)、ICT(感染対策チーム)、がん治療チーム、緩和ケアチームなど、専門チームに所属する薬剤師もいます。例えば抗菌薬の使い方を提案したり、抗がん剤の有害事象や支持療法についてディスカッションしたり、医師・看護師・管理栄養士・リハビリスタッフと一緒に患者さんの治療方針を考えます。
「病院薬剤師 仕事内容」でよく出てくる”チーム医療”という言葉は、まさにこうした場面のこと。病棟やカンファレンスの現場で、「薬の視点から診療にどう貢献するか」が仕事のコアになっていきます。
調剤から服薬指導まで:1日の流れ
病院薬剤師の1日は、調剤業務だけで完結するわけではありません。あくまで一例ですが、イメージとしては次のような流れになります。
朝は、その日に入院・退院・手術予定の患者さんの情報を確認し、必要な薬剤の準備や注射薬のセットからスタートします。午前中は調剤室での調剤・監査、病棟からの問い合わせ対応、抗がん剤や高カロリー輸液などの無菌調製を行うことも多いです。
午後は病棟へ上がり、担当病棟の患者さんのカルテや検査値を確認しながら処方チェック。必要に応じてベッドサイドで服薬指導を行い、飲み方・副作用・注意点などを直接説明します。患者さんから薬に関する不安や疑問を聞き出すのも大切な仕事です。
合間には医師からの相談や、DI(医薬品情報)業務として「この薬とこの薬の併用は?」「腎機能がこの値の時は?」といった質問に答える場面もあります。新薬や添付文書改訂の情報を院内に発信するのもDIの役割です。
夕方にはその日の処方監査・服薬指導の記録を整理し、翌日の入院予定の患者さんの処方を事前に確認して退勤、という流れになることが多いです。
病院薬剤師の年収・働き方のイメージ
「病院薬剤師 年収」で検索すると、調剤薬局やドラッグストアと比べて年収が低いという情報を見ることもあると思います。実際、初任給〜数年目の段階では、病院はやや低めに設定されていることが多いです。ただし、公立病院や大学病院では公務員給与や大学の給与体系に基づくため、安定性・昇給・福利厚生がしっかりしているケースも少なくありません。
当直や夜勤については、救急のある大きな病院では当直・オンコール体制が組まれていることがあります。一方で、規模の小さい病院や、勤務体制を工夫して当直がない薬剤部もあり、病院によってかなり差があります。
年収だけで見ると調剤薬局やドラッグストアに劣るように感じるかもしれませんが、
- 「幅広い症例・薬剤に触れられる」
- 「チーム医療での経験がキャリアの土台になる」
といった点は、長期的なキャリアを考えたときに大きな資産になります。
病院薬剤師に向いている人の特徴
病院薬剤師のやりがいは、「患者さんの治療に薬のプロとして深く関わり続けられること」です。しかし、合う・合わないもはっきり出やすい現場でもあります。
向いているのは、まず何よりも「勉強が苦にならない人」です。新薬、ガイドラインの改訂、治療レジメン、相互作用…覚えること・調べることは尽きません。それを「大変」ではなく「面白い」と感じられる人は、病院でどんどん成長していきます。
また、じっくりと患者さんやチームと向き合うことが好きな人にも向いています。病棟で顔なじみの患者さんが少しずつ回復していく様子を見守ったり、医師や看護師と相談しながら治療方針を微調整したりする中で、「チームの一員として自分が役に立っている」と実感できる場面が多いからです。
逆に、「一人で黙々と仕事を進めたい」「接遇やコミュニケーションは最低限でいい」というタイプには、病棟業務がストレスになることもあります。病院薬剤師は、説明や提案、調整など”人と関わる仕事”の比重が高いことを意識しておくと良いでしょう。
最後に
病院薬剤師の世界は、知れば知るほど奥が深く、「薬学生のうちにもっと見学に行けばよかった」とよく言われる領域でもあります。興味が少しでもあれば、実務実習や見学の機会を活かして、実際の雰囲気を体感してみてください。
CES薬剤師国試予備校 講師
アメリカの大学・大学院を卒業後、再受験にて薬学部に入学。再試・留年はなく、ストレートで国家試験にも合格。 卒業後は薬局薬剤師を経て、現在はCES薬剤師国家試験予備校の講師。