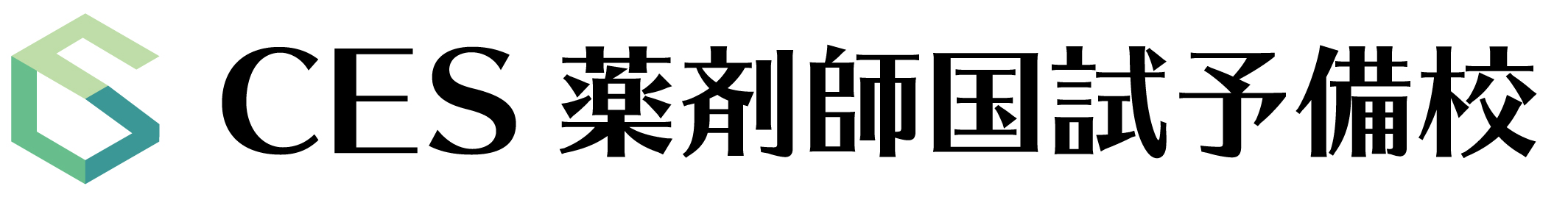第110回薬剤師国家試験「生物」の傾向と対策|出題の特徴と111回への学習戦略
第110回薬剤師国家試験「生物」分野の傾向と解説
「生物」問題の最新の出題傾向を分析し、第111回に向けた学習戦略を解説します。
「生物」における出題傾向
「生物」問題に関する出題傾向について、特に注目すべき点は以下の通りです:
- 臨床を意識した応用力
- 多分野の知識を統合する力の必要性
- やや難化傾向
ここ近年の薬剤師国家試験の出題傾向は変化しており、臨床現場を意識した応用問題が増加しています。
病態生理学、薬理学、薬物動態学などの知識を融合した問題が出題されていたため、多分野にまたがる統合的な応用力が必要となっています。
110回薬剤師国家試験は、109回と比較するとやや難化傾向でした。
図を用いた問題が出題され、薬理の知識も必要としたため難しく感じたと思われます。
検査項目に関する問題もあり、臨床を意識した問題が見られました。
では、110回薬剤師国家試験の問題を見ていきましょう。
第110回薬剤師国家試験「生物」分野の傾向
第110回薬剤師国家試験の「生物」分野では、臨床を意識した応用問題が増加し、多分野の知識を統合する力が求められました。ここでは、出題の特徴を分析し、次回試験に向けた対策を考えます。
必須問題の出題例
問13 真核生物において、転写開始の際にRNAポリメラーゼⅡの結合に必要なDNA上の領域はどれか。1つ選べ。
- イントロン
- エクソン
- プロモーター
- テロメア
- ターミネーター
プロモーターは、遺伝子の転写開始を調節するDNAの領域のことで、RNAポリメラーゼと基本転写因子群が結合することで転写反応が開始される。
他の選択肢については:
- 【選択肢1】:イントロン(介在配列)は、転写されるがスプライシングで除去され、最終的にはmRNAに含まれない塩基配列のことである。
- 【選択肢2】:エクソンは、転写され最終的にmRNAに含まれる塩基配列のことである。
- 【選択肢4】:テロメアは、真核細胞の染色体末端部分に相当し、複製のたびに短くなることが知られている。テロメアの長さはテロメラーゼによって維持されている。
- 【選択肢5】:ターミネーターは、転写(DNAからRNAを合成する段階)を終結させる目印となる塩基配列を含むDNA領域のことである。
理論問題の出題例
問114 ヒトにおける脂肪酸の生合成に関する記述として、正しいのはどれか。2 つ選べ。
- ミトコンドリアで行われる。
- アシル鎖の伸長過程で、補酵素としてNADHが利用される。
- クエン酸により促進される。
- アセチルCoAを前駆物質としてリノール酸が合成される。
- アセチルCoAをマロニルCoAに転換する反応が律速段階である。
アセチルCoAはミトコンドリアを通過できないので、オキサロ酢酸と結合してクエン酸となりミトコンドリアから細胞質に出る。ATP-クエン酸リアーゼにより、再びクエン酸は開裂されて脂肪酸合成のためのアセチルCoAを生成する。そのため、クエン酸により脂肪酸合成は促進される。
マロニルCoAは、アセチルCoAカルボキシラーゼによる炭酸固定反応によりアセチルCoAをカルボキシ化し生成される。この反応は脂肪酸合成における律速段階である。
他の選択肢については:
- 【選択肢1】:ヒトにおける脂肪酸の生合成はパルミチン酸まで細胞質ゾルで行われる。炭素数18 以上の脂肪酸は小胞体膜で行われる。なお、脂肪酸の分解反応であるβ酸化は、主にミトコンドリアマトリックスで行われる。
- 【選択肢2】:アシル鎖の伸長過程で、補酵素としてNADPHが利用される。
- 【選択肢4】:アセチルCoAを前駆物質として、アセチルCoAカルボキシラーゼが触媒する炭酸固定反応により不可逆的にカルボキシ基が導入(カルボキシ化)され、マロニルCoAが生成される。
実践問題の出題例
- レボドパは、ラセミ体である。
- 酵素A による反応は、アミノ基転移反応である。
- 酵素A による反応は、ビタミンB₆に由来する補酵素によって促進される。
- レボドパよりもドパミンの方が、脳内へ移行しやすい。
- 代謝物B は、レボドパ分子内のヒドロキシ基がメチル化されたものである。
酵素Aは芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素(AADC)、代謝物Bは3-O-メチルドパである。
ドパ脱炭酸酵素の補酵素であるビタミンB₆により、酵素Aによる末梢でのレボドパの脱炭酸が促進される。
代謝物Bは3-O-メチルドパであり、COMTによりレボドパの芳香環3位のヒドロキシ基がメチル化されたものである。
他の選択肢については:
- 【選択肢1】:レボドパは、ラセミ体ではない。レボドパは光学活性体であり、具体的にはL体(左旋性)の3-hydroxy-L-tyrosineである。ラセミ体は、光学異性体の等量混合物を指し、レボドパの場合、純粋なL体が使用されており、D体との混合物(ラセミ体)ではない。
- 【選択肢2】:酵素Aによる反応は、末梢性芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素(AADC)による脱炭酸反応である。
- 【選択肢4】:ドパミンは血液脳関門を通過できないので、末梢に投与しても無効である。一方、レボドパは芳香族 L-アミノ酸でありアミノ酸トランスポーターLAT1 により血液脳関門を通過できる。そのため、ドパ ミンよりもレボドパの方が、脳内へ移行しやすい。
第111回薬剤師国家試験に向けた対策
第110回薬剤師国家試験の生物分野では、臨床を意識した応用問題が増加し、多分野の知識を統合する力が求められました。第111回試験に向けて、以下のポイントを押さえた学習が重要です。
| 対策ポイント | 具体的方法 |
|---|---|
| 過去問の徹底分析 | 過去7年分の問題をしっかりと解き、基本事項の理解を深める |
| 統合的な理解の強化 | 病態生理・薬理・薬物動態を関連付けて学習する |
| 時事問題への対応 | 最新の生物学的トピックや臨床関連の話題をチェックする |
| インプット・アウトプット強化 | 模擬試験や問題演習を繰り返し、実践力を養う |
| 応用力の向上 | 多分野にまたがる問題への対応力を高める |
特に重要なのは、生体の仕組みと疾患のつながりを理解することです。各プロセスが病態や薬の作用とどう関係するのかを整理し、実践的に活用できるようにしましょう。
CES薬剤師国試予備校 講師
アメリカの大学・大学院を卒業後、再受験にて薬学部に入学。再試・留年はなく、ストレートで国家試験にも合格。 卒業後は薬局薬剤師を経て、現在はCES薬剤師国家試験予備校の講師。 薬剤師国家試験のゴロサイト『ゴロナビ〜薬剤師国家試験に勝つ〜』を運営中