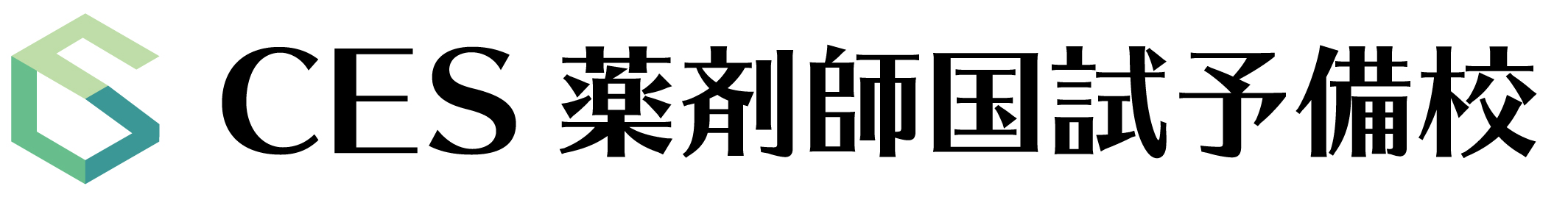第110回薬剤師国家試験「薬理」分野の傾向と解説 | 最新の出題分析と第111回に向けた対策
第110回薬剤師国家試験「薬理」分野の傾向と解説
最新の出題傾向を分析し、第111回に向けた効果的な対策法を解説します。
近年の薬剤師国家試験の傾向変化
近年、薬剤師国家試験の出題傾向は大きく変化しています。特に注目すべき点は以下の通りです:
- 臨床現場を意識した応用問題の増加
- 実務能力や判断力を試す問題の増加
- 症例ベースの問題や患者対応を想定した設問の増加
第110回薬剤師国家試験の薬理分野では、例年通り既出薬物の標的分子や作用機序を中心に出題されました。基本的な問題が多く、全体的な難易度は高くなかったという印象です。
特筆すべき点として、実践問題では心電図を読み取る問題が出題されました。心電図問題は病態・薬物治療では出題されていましたが、薬理分野では初出題となりました。
第110回国家試験の新出題傾向
ここでは、第110回試験で出題された新薬や作用機序に関する問題を見ていきましょう。
必須問題の出題例
問 33 尋常性乾癬の治療に用いられるセクキヌマブの標的分子はどれか。1 つ選べ。
- ホスホジエステラーゼⅣ(PDEⅣ)
- チロシンキナーゼ 2(Tyk2)
- ビタミンD受容体
- IL-12 及び IL-23
- IL-17A
【解答】5
セクキヌマブに関する記述である。セクキヌマブは、ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体であり、IL-17Aに結合し、その生物活性を中和する。
他の選択肢については:
- 【選択肢1】:アプレミラストに関する記述である。アプレミラストは、PDEⅣを阻害することにより、炎症細胞内でのcAMPを増加させ、IL-17、TNF-α、IL-23及びその他の炎症性サイトカインの発現を制御する。
- 【選択肢2】:デュークラバシチニブに関する記述である。デュークラバシチニブは、チロシンキナーゼ2(TYK2)阻害薬 である。TYK2の機能制御部位に結合し、この部位と触媒部位 の間の相互作用を安定化することで、インターロイキン(IL) -23、IL-12、I型インターフェロン(IFN)などで誘導される TYK2の活性化が阻害され、TYK2が介在する炎症や免疫応答 が抑制される
- 【選択肢3】:タカルシトールに関する記述である。タカルシトールは、ビタミンD受容体に結合し、表皮細胞の増殖抑制作用及び分化誘導作用を示す。
- 【選択肢4】:ウステキヌマブに関する記述である。ウステキヌマブは、ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体であり、IL-12及びIL-23を構成するp40タンパクサブユニットに結合してこれらを阻害する。
理論問題の出題例
問 154 抗てんかん薬に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ラコサミドは、電位依存性 Na⁺チャネルの緩徐な不活性化を促進して、神経細胞の過剰興奮を抑制する。
- スルチアムは、電位依存性 T 型 Ca²⁺チャネルを遮断して、欠神発作に特徴的な棘徐波複合の発生を抑制する。
- スチリペントールは、シナプス小胞タンパク質 2A(SV2A)に結合して、神経伝達物質の遊離を抑制する。
- ビガバトリンは、γ-アミノ酪酸(GABA)トランスアミナーゼを不可逆的に阻害して、脳内GABA 濃度を上昇させる。
- ルフィナミドは、グルタミン酸 AMPA 受容体を非競合的に遮断して、神経細胞における活動電位の発生を抑制する。
【解答】1, 4
他の選択肢については:
- 【選択肢2】:エトスクシミドに関する記述である。スルチアムは、脳内の炭酸脱水酵素を阻害し、神経細胞の過剰興奮を抑制する。
- 【選択肢3】:レベチラセタムに関する記述である。スチリペントールは、GABA取り込み阻害作用、GABAトランスアミナーゼ活性低下作用、脳組織中GABA濃度の増加作用及びGABAA受容体に対する促進性アロステリック調節作用により、GABA神経伝達を亢進する。
- 【選択肢5】:ペランパネルに関する記述である。ルフィナミドは、てんかん発作の原因となる過剰電荷を帯びている脳内ナトリウムチャネルの活動を調節することでナトリウムチャネルの不活性状態を延長し、抗てんかん作用を示すと考えられている。
実践問題の出題例
問 261 ヘリコバクター・ピロリの除菌療法において、ボノプラザン以外にラベプラゾールも用いられてきた。ボノプラザン又はラベプラゾールに関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
- ボノプラザンは、壁細胞における H⁺,K⁺-ATPase の発現を抑制する。
- ボノプラザンは、胃酸による活性化を必要としない。
- ボノプラザンは、弱酸性であり、壁細胞内に分子形として集積する。
- ラベプラゾールは、K⁺と競合して、壁細胞からの H⁺分泌を阻害する。
- ラベプラゾールは、H⁺,K⁺-ATPase とジスルフィド結合を形成する。
【解答】2, 5
他の選択肢については:
- 【選択肢1】:ボノプラザンは、可逆的でカリウムイオンに競合的な様式でH ⁺,K⁺-ATPaseを阻害する。
- 【選択肢3】:ボノプラザンは、塩基性が強く胃壁細胞の酸生成部位に長時間残存して胃酸生成を抑制する。
- 【選択肢4】:ボノプラザンに関する記述である。ラベプラゾールは、胃酸分泌細胞の酸性領域で活性体(スルフェンアミド体)となり、プロトンポンプ(H ⁺,K⁺-ATPase)のSH基と共有結合(ジスルフィド結合)を形成する。その結果、胃酸分泌を非可逆的に阻害して、持続的に胃酸分泌を抑制する。
第111回薬剤師国家試験に向けた対策
第110回薬剤師国家試験の薬理分野では、既出問題からの出題が多く比較的解きやすかったと考えられます。第111回に向けて効果的な対策を立てるためには、以下のポイントを押さえましょう。
| 対策ポイント | 具体的方法 |
|---|---|
| 過去問の徹底分析 | 過去7年分の問題をしっかりと解き、作用機序と薬の名前を一致させる |
| 周辺知識の強化 | 基本的な薬理作用だけでなく、関連する薬物の特徴も含めて理解する |
| アウトプット強化 | 模擬試験などを活用し、知識の定着を確認する |
| 新しい出題傾向の把握 | 心電図問題など、新たな出題傾向にも対応できるよう準備する |
特に重要なのは、作用機序と薬物名の一致です。各薬物がどのような標的分子に作用し、どのような機序で効果を発揮するのかを体系的に整理しておきましょう。
著者プロフィール
CES薬剤師国試予備校 講師
アメリカの大学・大学院を卒業後、再受験にて薬学部に入学。再試・留年はなく、ストレートで国家試験にも合格。 卒業後は薬局薬剤師を経て、現在はCES薬剤師国家試験予備校の講師。 薬剤師国家試験のゴロサイト『ゴロナビ〜薬剤師国家試験に勝つ〜』を運営中